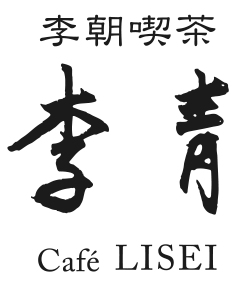工芸品が好きな方ならご存じかと思いますが、一言で「李朝」と言っても多種多様です。特にやきものでは「白磁」「黒高麗」「三島」「鶏龍山」など、李朝には多様なかたち、色、文様、親しまれた名称があります。型どおりに技を操るのではなく、どのような花をも引き立て、あるがままに花と遊ぶことを許す大らかさが李朝の持つ味と言えます。
朝鮮時代(1392-1910年)の文献にみられる「挿花」という言葉は、国王に下賜された冠帽の花飾りを意味します。花や枝葉をかたどった装飾を冠帽につけることは古くからの伝統で、ひとえに権威を象徴します。その一方、花が民衆の身近にあったことは、花のモチーフが生活品に溢れていることからも容易に想像できます。やきものに花を生ける行いが「道」となることはありませんでしたが、特に15世紀以降、白磁に花を挿して場を華やかにすることは、韓国では特に重要な意味を持っていました。
日本では華道の影響もあって、花は型を意識しながらも流れるように形作られるのが特徴だとすれば、韓国ではシンメトリーであることが重視され、常に正面を意識して挿すのが一般的でした。これは仏教が盛んとなった高麗時代からの名残で、献供花としての視覚的効果が引き継がれています。さらに花の見せ方と役割を特徴づけたのが、朝鮮王朝の建国理念ともなった朱子学(新しい儒学)でした。儒教の教化と儀礼を重視した朝鮮王朝では、17世紀以降、祖先崇拝のための祭祀(さいし)がますます浸透し、花の持つ視覚的な美しさに儒教の道徳的な規律や哲学が加味されていきました。
やきものと花は、儒教社会では官と民を問わず儀礼と深くかかわり、特に宮中では儀礼の回数があまりに多いため、そのほとんどは生花ではなく官職の「花匠」が製作する「假花」(「宮中彩花」。絹や韓紙によって造られる)が用いられるようになりました。そのような華やかな色彩を持つ朝鮮時代の花は、現代の私たちの思い描く「李朝と花」という、枯淡で静謐なイメージとはまったく異なります。
朝鮮時代の厳格な身分制度が、生活や工芸にも大きく影響を及ぼしていることは言うまでもありません。「李朝と花」という言葉からイメージされるのは、「官」を連想させる権威あるやきものや色鮮やかな花ではなく、無骨で崇高な「民」の精神に近く、それは柳宗悦たちが提唱した民芸の精神とも通じています。「民芸」という言葉が象徴する、愛情のこもった美の観点が「李朝と花」には注がれていると言えます。
やきものを見る時に、朝鮮時代の虐げられた「民」を思うほどの哀愁に浸りたくはありませんが、「李朝」と称されるやきものは一貫して形にどこか緩みがあります。かつて「官」が目指した厳格な儒教ではなく、社会の底辺にある、あるがままの「素」が、あるいは民の心が、「李朝と花」のイメージへと昇華していることに気づかされます。


韓国・国立古宮博物館の展示風景(2014年)